アレルギー性鼻炎の種類&原因|訪問看護の場での対応方法・予防法
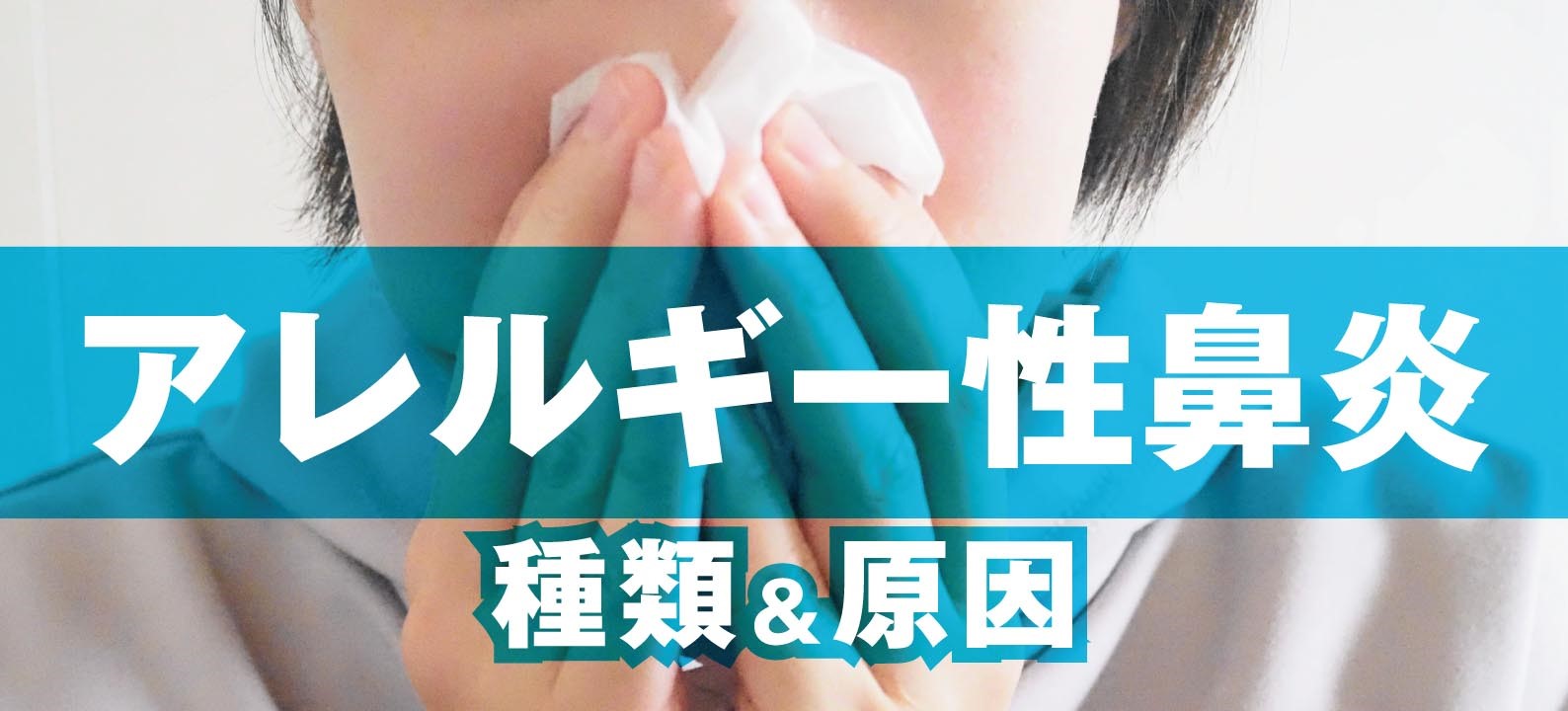
くしゃみ、鼻水、鼻詰まりといった症状により生活の質が低下するアレルギー性鼻炎は、通年性や季節性などが存在し、原因には住環境や食生活の変化、大気汚染などがあります。
訪問看護では、利用者さんの生活環境や習慣を踏まえた柔軟な対応が求められます。この記事では、アレルギー性鼻炎の種類や原因、対処法からケア方法まで解説します。本記事で解説する内容を、ご自身の健康管理や、利用者さんとそのご家族のアセスメントに役立ててください。
目次
アレルギー性鼻炎の症状
アレルギー性鼻炎では、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりといった症状が見られます。
- くしゃみ
回数が多く連続して起こりやすいことが特徴です。 - 鼻水
風邪のときのように粘り気はなく、無色透明でサラサラとしている傾向にあります。 - 鼻詰まり
鼻粘膜の腫れによって起こります。
こうした症状が長引くと、
- 頻繁に鼻をかむことで粘膜が傷ついて鼻出血を起こす
- 集中力が低下する
- 睡眠不足になる
- イライラする
といった症状も現れ、生活の質が著しく低下することもあるでしょう。
また、通常は鼻で呼吸をすると外気が鼻の中で適度に加湿され、体内に取り込まれます。しかし、鼻詰まりによって口呼吸になると、乾燥した空気がそのまま体内に入り、感染リスクも高まります。
アレルギー性鼻炎の種類
アレルギー性鼻炎は、アレルゲン(抗原:アレルギーの原因物質)が鼻粘膜から侵入しマスト細胞上のIgE抗体に結合することによって症状が引き起こされる抗原抗体反応(I型アレルギー)の一種です。これには、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、ダニやホコリといったアレルゲンが原因となり、1年を通して症状が現れる「通年性アレルギー性鼻炎」です。もうひとつは、スギやヒノキなどの花粉が原因となり、花粉の飛散する時期に限定して症状が現れる「季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)」です。いずれのタイプでも、くしゃみ、透明で水っぽい鼻水、鼻詰まりといった症状が現れます。
なお、寒暖差によって引き起こされる「血管運動性鼻炎」と呼ばれるタイプもありますが、これは非アレルギー性の鼻炎です。
アレルギー性鼻炎の環境要因
アレルギー性鼻炎を発症しやすい環境要因を見ていきましょう。
住環境
現代の住宅は気密性が高いため、換気が不十分な状態が続くと、ダニやハウスダストといったアレルゲンが室内に溜まりやすくなります。さらに、高気密・高断熱住宅では梅雨時に室内の湿度が上がりやすく、アレルゲンとなるカビの発生を引き起こす要因に。そのため十分に換気をする、除湿機を使用するなど、室内の風通しをよくして適切な湿度を維持することが大切です。湿度が60%を超えると、カビやダニが発生しやすくなり、アレルギー性鼻炎をはじめとしたアレルギー疾患の原因となりますので、湿度の目安は60%以下とします。
また、現代社会では、単身世帯や共働き世帯が増え、掃除をする時間が限られている家庭も多くなっています。特に人が頻繁に行き来する廊下や洗面所などでは、目に見えないハウスダストが蓄積します。これらの場所を定期的に掃除し、アレルゲンを減らすことが重要です。また、観葉植物の葉や照明器具のカバー、天井などもハウスダストが溜まりやすいためこまめにチェックするようにしましょう。
食生活の変化
加工食品や添加物を多く含む現代の食生活が免疫バランスを崩し、アレルギー反応を引き起こしやすい体質を作るとされています。
排気ガス・PM2.5など
排気ガスやPM2.5などの大気汚染物質も、アレルギー性鼻炎を悪化させる要因です。特に都市部では、自動車の排気ガスや微細な粒子状物質が鼻の粘膜に炎症を引き起こし、症状を増悪させることがあります。
アレルギー性鼻炎による鼻詰まりの対処法
自宅では、生理食塩水や市販の鼻腔洗浄キットを使った鼻腔洗浄が有効で、アレルゲンの除去や粘膜の清潔を保つことができます。また、加湿器の使用や濡れタオルを部屋に干すことで部屋の湿度を保ち、鼻粘膜の乾燥を防ぐことも大切です。ただし、加湿器の水槽やフィルター、濡れタオルはカビの発生源となる可能性が高いため、加湿器は定期的に清掃し、部屋に干す濡れタオルも清潔なものにこまめに交換するなど、カビを防ぐための対策を欠かさずに行いましょう。
住環境の改善や生活習慣の見直しも、症状の軽減に大きな役割を果たします。しかし、現実には住環境を理想的に整えることが難しいケースも多いため、「できる限り改善に努める」という柔軟な姿勢が重要です。たとえば、部屋の掃除や換気を定期的に行うだけでも、ハウスダストやダニなどのアレルゲンを減らすことができます。また、カーテンや布団など、アレルゲンが溜まりやすい箇所の洗濯頻度を増やすよう伝えるのも良いでしょう。
そのほか、外出時にマスクを着用して花粉やホコリの吸入を防止したり、帰宅後に衣服をすぐに着替えてシャワーを浴びることでアレルゲンの付着を最小限に抑えたりなど、利用者さんの状況や状態に応じて対応策を検討してください。
アレルギー性鼻炎の治療法
症状がひどく改善しない場合は、医療機関での治療が必要です。アレルギー性鼻炎の治療法には、薬物療法とアレルゲン免疫療法、手術療法があります。
- 薬物療法
抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬、鼻噴霧用ステロイド薬や経口ステロイド薬、点鼻用血管収縮薬などを処方します。 - アレルゲン免疫療法
アレルゲンを少量から徐々に増量して体内に取り込むことで、アレルゲンに対する体の過剰な反応を抑える治療法です。この治療法は、数年以上の期間が必要で、根気強く続けることが求められますが、薬物療法の副作用で治療の継続が困難だったり、薬物療法だけでは症状が十分に改善しなかったりする場合に選択されます。 - 手術療法
鼻の粘膜をレーザーで凝固しアレルギー反応が鼻粘膜でおきにくくする下鼻甲介粘膜焼灼術や鼻腔の形を整えて鼻詰まりを改善する粘膜下下鼻甲介骨切除術、鼻漏改善やくしゃみ軽減のための後鼻神経切断術などがあります。
日常での鼻詰まり解消法
日常生活での鼻詰まり解消には、簡単に取り入れられる方法がいくつかあります。入浴することで体が温まり、血行が促進されるため、鼻詰まりの改善が期待できます。お湯から立ち上る蒸気が鼻の奥まで届き、鼻粘膜を潤してくれる効果もあります。また、蒸しタオルを鼻に当てる方法もおすすめです。タオルをお湯で濡らして絞り、鼻周辺に軽く当てると血流が良くなり、鼻詰まりを和らげる効果が期待できます。
子どもの鼻詰まりは、自分で鼻を上手にかむことができない場合、症状が悪化しやすいです。鼻水吸引器を使って鼻水を吸引することで、鼻詰まりを軽減させることができます。吸引器は電動タイプや手動タイプなどさまざまな種類があります。
快適な睡眠の工夫
上半身を高くして寝ることで、重力の影響で鼻の通りが良くなり、鼻詰まりが軽減されます。枕を少し高くしたり、リクライニングできるベッドを活用したりしましょう。
また、上述したように乾燥による鼻粘膜の刺激を防ぐためには、部屋の湿度を保つことが大切です。さらに、マスクをつけると、鼻周辺の湿度が保たれ、鼻の乾燥を防ぐと同時に外気の冷たさを和らげることにもつながります。
* * *
アレルギー性鼻炎は、症状の辛さが日常生活に大きな影響を及ぼしますが、適切な治療や住環境の改善などによって、その負担を軽減することが可能です。訪問看護では、利用者さんの生活環境に合わせた提案やケアが重要です。今回紹介した対処法や予防策を活用し、アレルギー性鼻炎の悩み解消をサポートしましょう。
| 編集・執筆:加藤 良大 監修:瀬尾 達(せお わたる)  医療法人瀬尾記念会瀬尾クリニック理事長。耳鼻咽喉科専門医。 クリニックでの診療の他、京都大学医学部講師や大阪歯科大学講師を兼任。 祖父から代々の耳鼻科医の家系。兄は、聖マリアンナ医科大学耳鼻科教授。 テレビやマスコミ出演多数。 |
【参考】
〇東京都福祉保健局.「健康・快適居住環境の指針― 健康を支える快適な住まいを目指して ―」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/web_zenbun1
2025/1/30閲覧
〇東京都福祉保健局「健康・快適居住環境の指針」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/web_arerugen_taisaku_kenkai_sisin
2025/1/30閲覧
〇日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会「アレルギー性鼻炎ガイド2021年版」
http://www.jiaio.umin.jp/common/pdf/guide_allergy2021.pdf
2025/1/30閲覧







