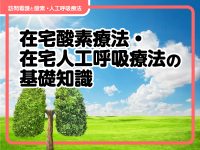特集
会員限定
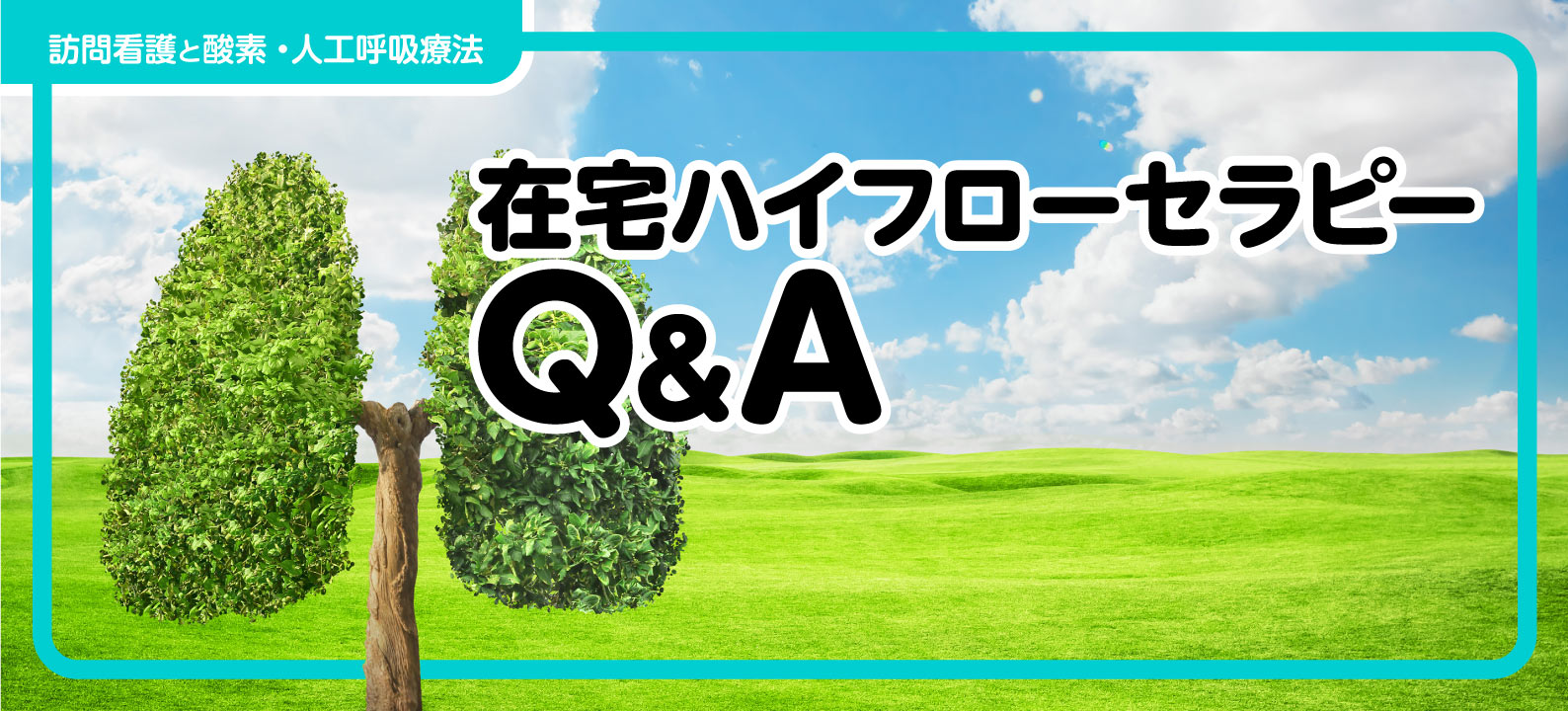
在宅において患者が「高流量鼻カニュラ酸素療法」(high flow nasal cannula oxygen therapy:HFNC)を継続していくためには、不快感やトラブルへの早期対応とアドヒアランスを維持するための支援が必要不可欠です。そこで、今回は、装着時のコツや不快・トラブル時の対応、アドヒアランスを支えるための精神的支援のポイントをご紹介します。
Q1 訪問看護で初めて在宅HFNCの患者さんを担当することに。使…
在宅ハイフローセラピー Q&A/装着のコツ、トラブル対応、アドヒアランス支援
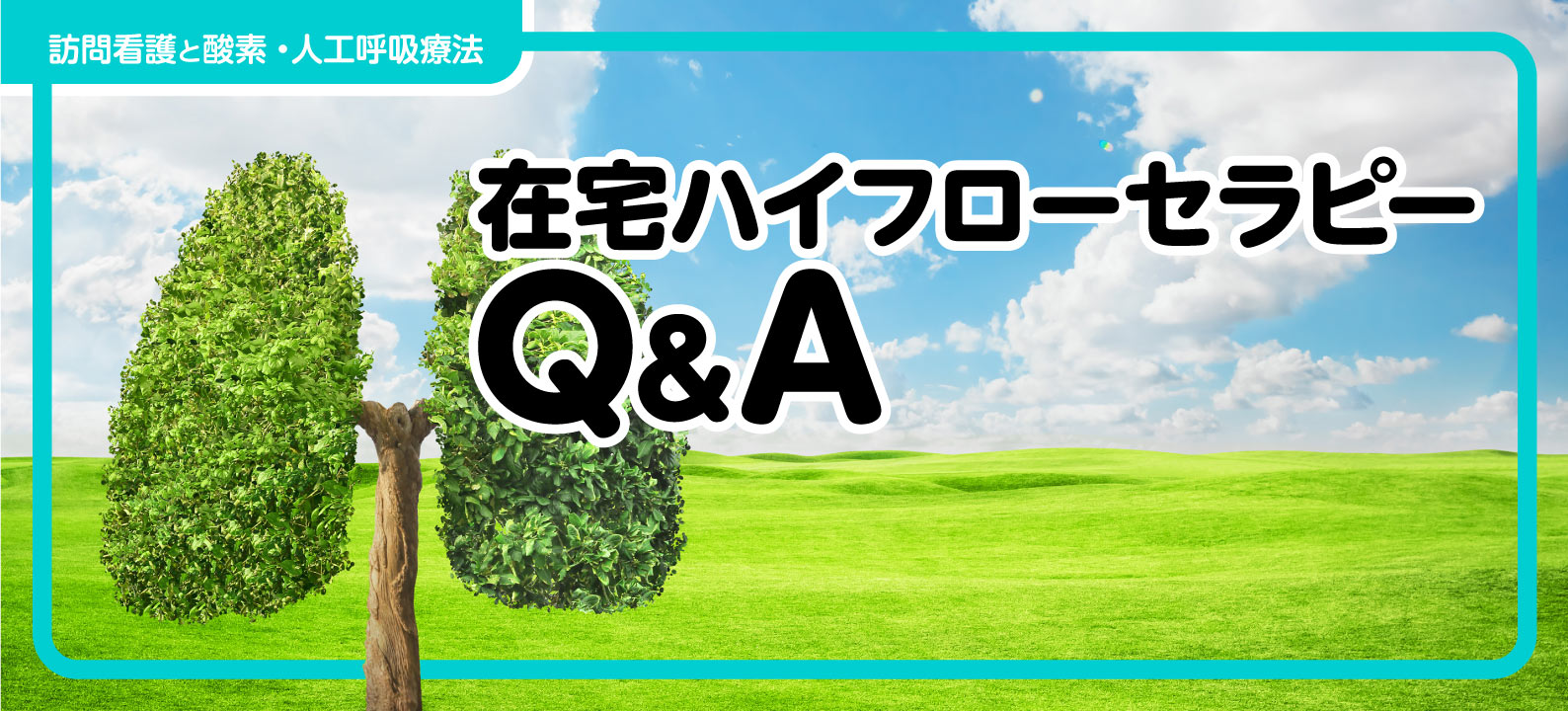
在宅において患者が「高流量鼻カニュラ酸素療法」(high flow nasal cannula oxygen therapy:HFNC)を継続していくためには、不快感やトラブルへの早期対応とアドヒアランスを維持するための支援が必要不可欠です。そこで、今回は、装着時のコツや不快・トラブル時の対応、アドヒアランスを支えるための精神的支援のポイントをご紹介します。
Q1 訪問看護で初めて在宅HFNCの患者さんを担当することに。使…