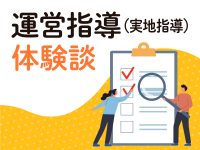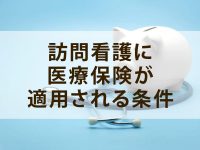運営指導(実地指導)制度解説 名称変更で何が変わったの?

2022年度から「実地指導」は「運営指導」に名称が変更されました。この変更によって何が変わったのでしょうか。この記事では、訪問看護事業に関わる方のために変更ポイントだけでなく、行政機関による運営指導の意味や内容、向き合い方についてお伝えします。
目次
「運営指導」とは事業所を正しい方向へ導く制度
「運営指導」とは介護保険法に基づき、行政機関が事業所に対し、適正な事業運営が実施されているか指導するものです。もともと「実地指導」と呼ばれていましたが、2022年度から、指導に際しオンライン会議ツールの活用が明記され、指導場所が必ずしも「実地」ではなくなることから名称が「運営指導」に改められました。
なお、ここでいう行政機関とは、利用者が介護サービスを受けた場合にその費用を支払う「保険者」でもあり、介護サービスを行う事業所に対し、指定または許可した事業所を所管する「指定等権者」としての立場にあります。
いうまでもなく介護保険事業は、保険料と公費で賄われる公益性の高いサービスです。介護保険法(以下「法」とします)の第1条には、その目的として介護や看護、医療が必要な人の「尊厳の保持」、および「自立した日常生活の支援」が謳われています。したがって、サービスの担い手である事業所は、利用者さんに対し、この目的を果たすよう適切にサービスを行わなくてはなりません。
そして、行政機関は、各事業所がこうした責任を果たし、適正にサービスを行うことができるよう指導・支援する必要があります。そのため、行政は定期的に指導に入り、事業所を正しい方向に導いているのです。
「運営指導」と「監査」はまったく違う
行政機関が行う指導には、運営指導とは別に「監査」と呼ばれるものがあります。言葉がよく似ているので混同されるケースがあるようですが、まったく違います。ここで、介護保険制度における指導監督の全体像について確認しておきましょう。
厚生労働省による「介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月)」を見ると、指導監督について次のように説明されています。「介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保のため、法第23条又は法第24条に規定する権限(中略)に基づき行う介護保険施設等に対する『指導』、不正等の疑いが認められる場合に行う法第76条等の権限(中略)に基づき行う『監査』により行われます」1)。ここで言う「指導」とは運営指導を含みます。
指導と監査の違いについて具体的に説明しましょう。
(1)指導
指導には、集団指導と運営指導があります。
■集団指導
集団指導は事業所を1ヵ所に集めて開催されます。現場において対応が必要な法改正や留意点等、事業運営について必須の情報を伝達・共有することで、介護保険サービスの質の確保と保険給付の適正化を目的としています。
■運営指導
一方、運営指導は事業所ごとに行われます。先述のとおり、介護サービスの質、運営体制、介護報酬請求の実施状況などの確認のために実施するもので、契約書や計画書・記録等の文書提示の求めや質問によって行われます。
(2)監査
監査とは、事業所に運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合、またそのおそれがある場合に行われる「強制調査」です。行政は違反や不正等の事実関係を明確にした上で、それらが認められる場合、勧告または指定取消等の行政処分を行います。
*
指導は、あくまで事業所側の任意の協力によるものですが、監査には強制力がある点が最大の違いです。立入検査の権限も監査に含まれます。運営指導で違反や不正等の疑いがあった場合、運営指導では立入検査ができないため、途中で監査に切り替えて事実確認が行われるケースもあります。
「運営指導」に移行し「効率化」が強化
「運営指導」に変更するに伴い強化されたこと、それは「効率化」です2)。ポイントは次の3つ。冒頭で述べた「オンラインの活用」、そして「ローカルルールの是正」と「実施頻度の明記と推進」です。
(1)オンラインの活用
運営指導は基本的に実地で行うことが想定されていますが、最低基準等運営体制指導や報酬請求指導については、実地でなくとも確認できる内容であるため、オンライン等の活用が可能であることが明記されました。
(2)ローカルルールの是正
効果的、効率的な指導を推進するため、自治体ごとの異なる指導ルール(いわゆるローカルルール)について是正が図られました。具体的には次のようなことが明記されました。
・標準的な確認項目や確認文書(※)以外の項目は原則として確認しないこと
※厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月)」の別添資料「確認項目及び確認文書」にサービス種別ごとの確認項目と確認文書がまとめられています。例えば、訪問看護における「サービス提供記録」であれば「訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか」、「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」が確認項目として挙げられています。
・1回の指導にかかる時間をできる限り短縮すること
・提出を求める書類の写しは1部とすること
・自治体がすでに保有している文書は再提出を求めないこと
(3)実施頻度の明記と推進
運営指導の実施頻度は、原則、指定または許可の有効期間(6年)内に少なくとも1回以上と定められました。
運営指導は業務改善のチャンス
運営指導と聞くと、どうしても身構えてしまい、指導通知が来ると「運が悪い」と感じたり、慌ててしまったりすることがあるかもしれません。ですが、これまで解説してきたとおり、運営指導は正しく質の高いサービスをしっかり利用者さんに提供できているかどうかを外部の目で点検してくれる機会です。「業務の確認や改善のチャンス」とプラスに受け止められるとよいでしょう。
もし、運営指導で法令違反があった場合、軽微なものであれば口頭、あるいは後日書面で改善点が指摘されます。また、不正請求ではなく、単なる請求上の誤りがあった場合は、過誤調整(報酬返還)を要することもあります。いずれにせよ、これらに速やかに対応し改善すれば、運営指導の段階ではそこで終了です。指定取消といった厳しい処分に進むことはまずないため、安心してください。
「運営指導対策」という言葉を見聞きしますが、手を抜いたり、即席で対策が完了したりといった楽ができるような方法は存在しません。真に有効であり、唯一の対策は「普段からきちんとやる」ことにほかならないのです。それは、利用者さんとの契約や同意の書面を忘れずに取り交わす、利用者さんごとに計画をしっかり協議し立案する、計画に沿ったケアを提供するといった当たり前のことであり、これらを丁寧に記録化していく作業が大切です。日々の業務をきちんとこなすことが運営指導の準備につながります。
また、運営指導にリニューアルしたことで効率化の観点からチェックするポイントが絞られ明確化されました。各自治体から配布されている自己点検票が役に立ちます。問われるポイントが絞られたことから、事業所側としてはより対応しやすくなったといえるでしょう。
| 執筆:外岡 潤 介護・福祉系 弁護士法人おかげさま 代表弁護士 ●プロフィール 弁護士、ホームヘルパー2級 介護・福祉の業界におけるトラブル解決の専門家。 介護・福祉の世界をこよなく愛し、現場の調和の空気を護ることを使命とする。 著書に『介護トラブル相談必携』(民事法研究会)他多数。 YouTubeにて「介護弁護士外岡潤の介護トラブル解決チャンネル」を配信中。 https://www.youtube.com/user/sotooka 編集:株式会社照林社 |
【参考・引用】
1)厚生労働省.「介護保険施設等運営指導マニュアル 令和4年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000949269.pdf
2023/3/20閲覧
2)厚生労働省.「介護保険施設等指導指針」(2022年3月31日)