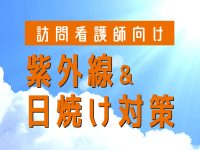日焼け(日光皮膚炎)の基礎知識 肌への悪影響や紫外線アレルギーとの違い

強い日差しのもとで肌をさらすと、日焼け(日光皮膚炎)が起きることがあります。当然ながら、日焼けは肌が褐色や黒色に変わるだけではなく、肌にさまざまな悪影響を及ぼすため、なるべく避けることが大切です。本記事では、改めて日焼けによる肌への悪影響や皮膚がんとの関係、対策などについて詳しく解説します。訪問看護師さん自身の日焼け対策はもちろん、利用者さんのケアにもぜひ役立ててください。
目次
日焼け(日光皮膚炎)とは
日焼けは医学用語で「日光皮膚炎」といい、紫外線の影響で肌に熱傷を負った状態を指します。
日焼けには、肌が赤くなる「サンバーン」と肌が黒くなる「サンタン」があります。紫外線を浴びてから8~24時間後にサンバーンが現れ、その2~3日後にサンバーンが消失してサンタンが生じます。
- サンバーン:紫外線の影響でダメージを受けた細胞が修復される過程で発現した遺伝子により、血管が膨張して起きる症状
- サンタン:紫外線によって生じた炎症の影響でメラノサイトが刺激され、メラニンが大量に生成されて皮膚に沈着して生じる症状
日焼けの症状や健康・美容面への影響、対処法などについて詳しく見ていきましょう。
症状
日焼けをすると、紫外線の影響で炎症が起こり、ヒリヒリとした痛みや火照りなどが起こります。真夏の海のような強い紫外線を浴びる環境に長時間滞在すると、皮膚の赤み、水ぶくれやむくみ、などが生じる恐れがあります。日焼けの程度によっては、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。
健康・美容面への影響
紫外線は、肌の弾力成分であるコラーゲンやエラスチンを破壊したり変性させたりすることで、しわやたるみなどを引き起こします。長年にわたる紫外線ダメージが蓄積すると、シミが作られ、実年齢よりも老けて見えるケースもあるでしょう。また、皮膚症状に伴って熱中症様症状の頭痛や吐き気、発熱などを引き起こす場合もあります。
紫外線の健康面への影響において、最も注意すべきは「皮膚がん」でしょう。紫外線を浴びる時間が長くなればなるほどに、皮膚がんの発症リスクが高まるといわれています。すべての皮膚がんが紫外線の影響を受けるわけではありませんが、次のようにさまざまながんに関連しています。
- 日光角化症
- 有棘細胞がん
- 基底細胞がん
- メラノーマ
紫外線を浴びることですぐに皮膚がんを発症するのではなく、長年にわたり受けてきたダメージによって細胞が損傷を受けた結果、発症するリスクが高まります。そのため、少しでも早く紫外線対策を始めて、紫外線ダメージを減らすことが大切です。
対処法
日焼けした場合は、なるべく早く濡れタオルや氷水を入れた袋などで冷やしましょう。痛みを和らげるとともに、皮膚への紫外線ダメージを抑えることができます。痛みがある程度おさまったら、クリームで肌を保湿・保護します。
水ぶくれができた場合は、清潔なガーゼで保護した上で、医療機関で治療を受けましょう。主な治療方法は、炎症を抑え、感染症を防ぐ外用薬や内服薬を使用します。
日焼け(日光皮膚炎)した場合の生活の注意点
日焼けをした肌は非常にデリケートで、通常は問題にならない刺激でも大きな影響を受ける恐れがあります。そのため、なるべく肌を休ませて、化粧品は使用しないことが大切です。また、着替えの際に肌をこするとダメージを受ける場合があるため、ゆっくりと着脱し、肌に負担をかけないようにしましょう。熱いお風呂やシャワーの強い水圧などにも注意が必要です。
日焼けによる炎症がおさまるまでは、できるだけ日光を避けるようにしましょう。直射日光にさらされることで痛みやかゆみが増す可能性があります。外出する際には帽子や長袖の服を着用したり、日焼け止めを使用したりします。
紫外線アレルギーと日光皮膚炎の違いは?
紫外線アレルギーは、日光アレルギーや日光過敏症、光線過敏反応とも呼ばれ、日光を浴びることでかゆみや発疹、水ぶくれなどが発生したり悪化したりするアレルギー性皮膚疾患の総称です。日光皮膚炎は紫外線が肌にダメージを与えることで起きるものであるのに対し、紫外線アレルギーは特定の物質や成分と紫外線が反応して生じるものです。
紫外線アレルギーは内因性と外因性に分類され、それぞれ次のような種類があります。
内因性
詳しいメカニズムは解明されていないものが多く、紫外線だけではなく遺伝やほかの病気が関係しているといわれています。内因性の紫外線アレルギーの主な種類と症状は次のとおりです。
- 日光蕁麻疹……日光が当たったところに蕁麻疹ができる
- 慢性光線性皮膚炎……光が当たったところに赤みのある隆起した湿疹ができる
- 色素性乾皮症……高い確率で皮膚がんを発症する難病指定されている病気。日光が当たったところが乾燥したり非常に多数のシミができたりする
外因性
外因性の日光アレルギーには、光アレルギー性と光毒性の2つのメカニズムがあります。光アレルギー性は、紫外線とアレルゲンが化学反応を起こすことで生じるものです。赤みを伴う腫れや発疹、水ぶくれ、かゆみなどが現れます。
光毒性は、薬や香水などに含まれる物質が紫外線の影響を受けることで体内で活性酸素が生成され、これが細胞を攻撃して皮膚炎を引き起こすものです。赤みや腫れ、表皮剥離(皮剥け)、色素沈着などが現れます。外因性の光アレルギーの主な種類は次のとおりです。
- 光接触皮膚炎……外用薬や香料、日焼け止めなどの成分が原因となって発疹やかゆみ、水ぶくれなどが起きる
- 光線過敏型薬疹……一部の利尿薬や降圧剤、抗ヒスタミン剤、抗精神病薬などが紫外線に反応することで赤みやかゆみ、発疹、水ぶくれなどが起きる
日光皮膚炎と紫外線アレルギーはいずれも紫外線対策が重要
日光皮膚炎と紫外線アレルギーは、いずれも紫外線を浴びないことで予防できます。完全に紫外線を防ぐことは難しいものの、帽子、日傘、アームカバー、日焼け止め、サングラスなど、さまざまなアイテムを使うことで、紫外線量を抑えることが可能です。
日焼け止めは、以下を参考にSPFとPAが適切なものを選ぶ必要があります。
日常生活……SPF5、PA+
軽い屋外での活動やドライブ……SPF10、PA++
炎天下でのスポーツや海水浴……SPF20、PA+++
熱帯地方での屋外活動……SPF30以上、PA+++
また、日焼け止めは3時間に1回程度の頻度で塗り直しましょう。顔であれば真珠2個分程度の量をしっかりと伸ばします。日焼け止めの量が足りていない場合や、汗で流れ落ちたのに塗り直さないような場合、十分な効果を得られません。
* * *
日焼け(日光皮膚炎)は、シミやしわ、たるみなどの原因になるだけではなく、皮膚がんのように命に関わる病気との関連が深いため、普段から十分に紫外線対策をしておく必要があります。今回、解説した内容を自身の日焼け対策や利用者さんのケアにぜひ役立ててください。
| 編集・執筆:加藤 良大 監修:吉岡 容子 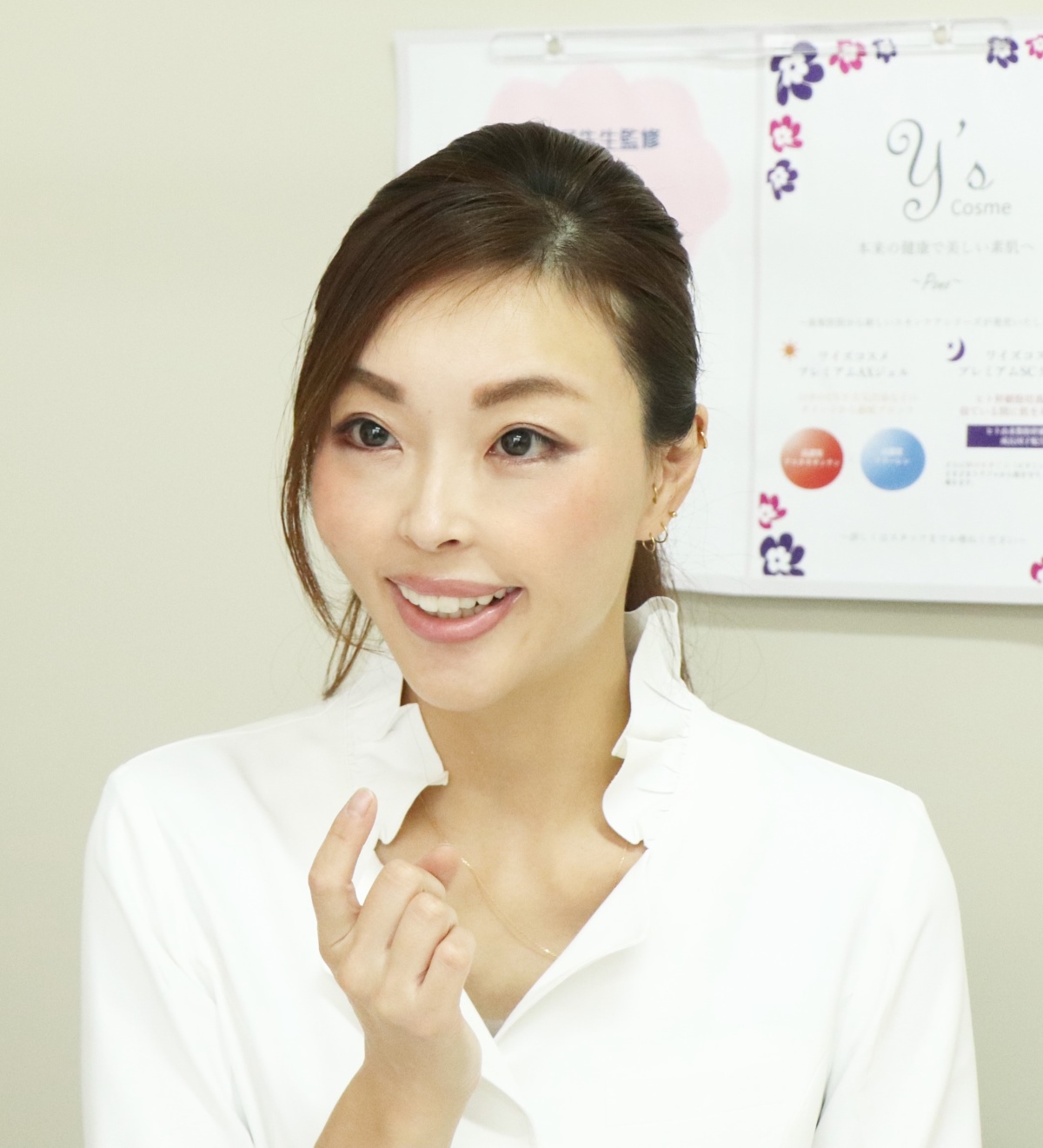 医療法人容紘会高梨医院 院長 東京医科大学医学部医学科を卒業後、麻酔科学講座入局。 麻酔科退局後、明治通りクリニック皮膚科・美容皮膚科勤務。院長を務め、平成24年より医療法人容紘会高梨医院皮膚科・ 美容皮膚科を開設。 院長として勤務しています。 |
【参照】
〇一般社団法人千葉医師会「日焼けから肌を守りましょう」(2011年8月26日)
https://www.chiba-city-med.or.jp/column/003.html
2024/6/14閲覧
〇公益社団法人日本皮膚科学会「Q4日焼けはどうして起こるのですか?」
https://www.dermatol.or.jp/qa/qa2/q04.html
2024/6/14閲覧
〇公益社団法人日本皮膚科学会「Q13サンスクリーン剤の使い方」
https://www.dermatol.or.jp/qa/qa2/q13.html
2024/6/14閲覧